
法改正概要LEGAL AMENDMENT
全国社会保険労務士政治連盟は、わが国社会の大きな変化と共に、時代に合った法律が施行されるよう取り組んでまいりました。その法改正の概要をご覧ください。

オイルショック【昭和48年】
第四次中東戦争を契機に原油価格が高騰。トイレットペーパーの買い占めが起こった。

男女雇用機会均等法【昭和60年】
企業の事業主が募集・採用・解雇などにあたり、性別を理由とした差別を禁止した。

バブル崩壊【平成三年~平成五年】
1980年代後半に起こった土地価格上昇の「バブル」が弾け、不景気への入り口となった。
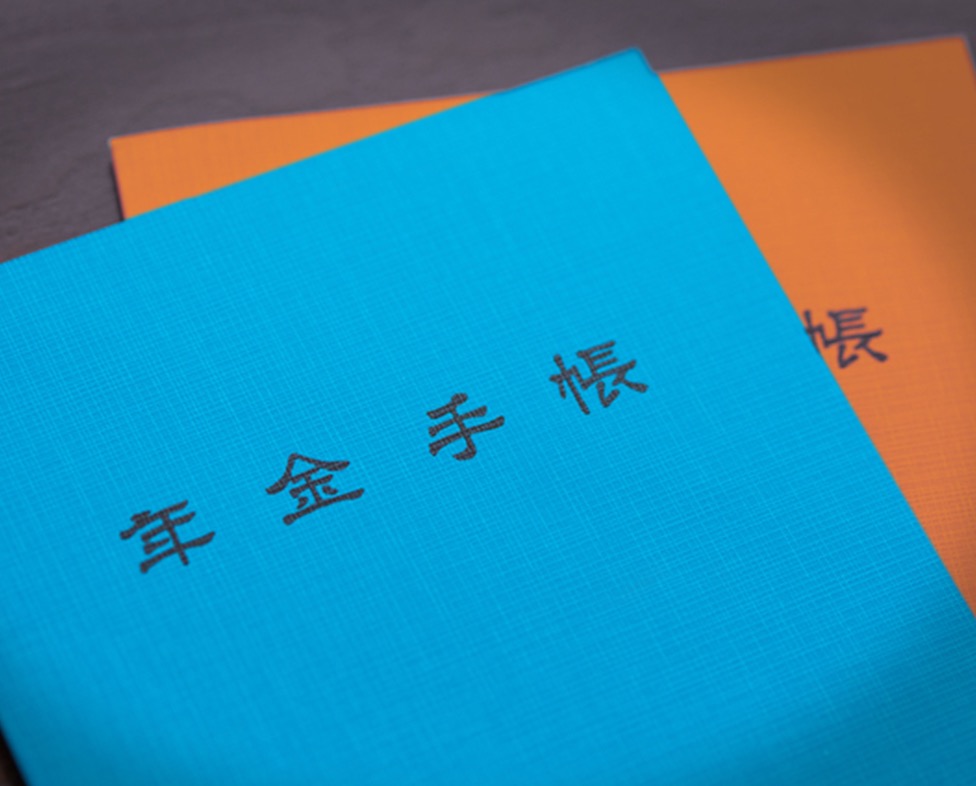
年金記録問題【平成19年】
基礎年金番号に統合されていない記録約5,095万件が明らかに。ここからねんきんネットなどが進んでいった。

リーマンショック【平成20年】
サブプライムローン危機から米投資銀行リーマンブラザーズが経営破綻。世界的な金融危機と不況につながった。

東日本大震災と
福島第一原発事故【平成23年】
死者・行方不明者18,000人以上。原発事故により、エネルギー政策が大転換。サプライチェーンの寸断で製造業に大打撃。

働き方改革関連法の施行【平成31年】
残業時間の上限規制、有給休暇取得の義務化、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保など。働き方の多様化が進む。
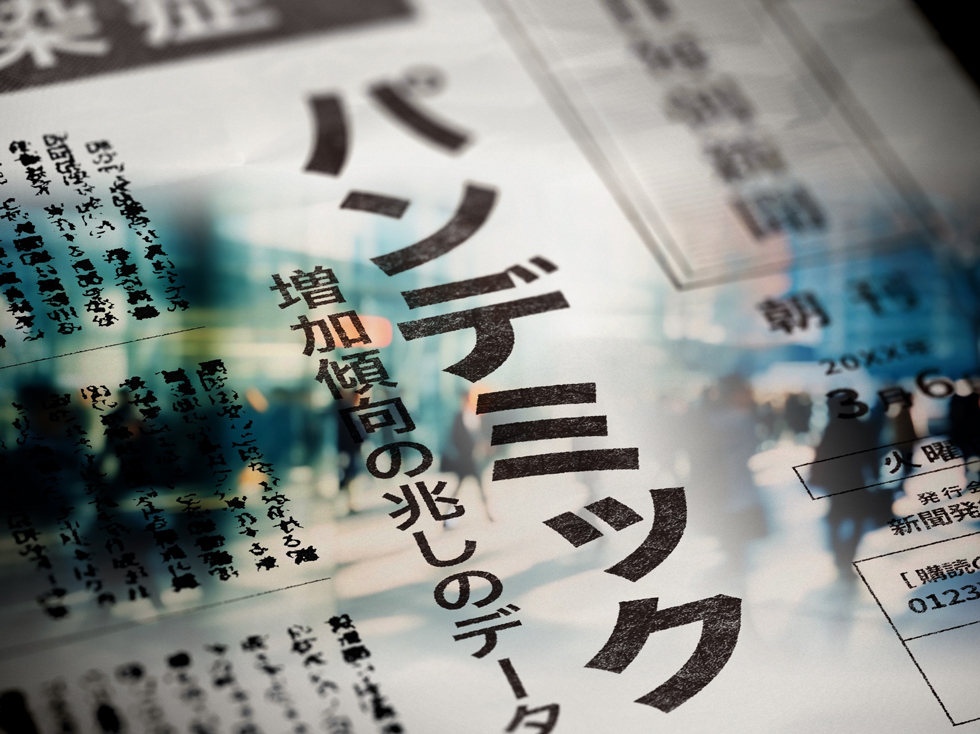
新型コロナウイルスの
パンデミック【令和2年〜】
緊急事態宣言、外出自粛、経済活動の制限。観光・飲食・航空業界が大打撃。テレワーク・DX(デジタル化)が急速に普及した。

いわゆる2025年問題
(高齢化社会の本格化)【令和7年】
団塊世代が後期高齢者に。医療・介護・年金制度の持続性が課題。労働力不足と社会保障費の増加が懸念される。
-
社会保険労務士法施行
【昭和43年施行】
-
第1次法改正 【 昭和53年5月20日公布 昭和53年9月1日施行 】
Ⅰ.提出代行業務の追加
社会保険労務士の業務に、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行業務を加えたこと。
Ⅱ.社会保険労務士会の設立等
- 1. 社会保険労務士は、社会保険労務士会を都道府県の区域ごとに一個設立することができることとしたこと。
- 2. 主務大臣の社会保険労務士会の適正な運営を確保するために必要な監督権限を定めたこと。
Ⅲ.連合会の設立等
- 1. 全国の社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会(連合会)を主務大臣の認可を受けて設立できることとしたこと。
- 2. 連合会の意見の具申
連合会は、主務大臣に対し、社会保険労務士制度の改善に関する意見又は労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができることとしたこと。
Ⅳ.社会保険労務士会及び連合会の行政機関への協力
主務大臣及びその他労働社会保険諸法令の施行に当たる行政機関は、これらの法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他の必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができることとしたこと。
-
第2次法改正 【 昭和56年6月2日公布 昭和57年4月1日施行 】
Ⅰ.社会保険労務士の職責の明確化
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で誠実にその業務を行わなければならない旨を規定し、社会保険労務士の職責を明らかにしたこと。
Ⅱ.提出代行事務の範囲の拡大
社会保険労務士の提出代行事務の範囲に労働者、年金受給権者等の個人を含むすべての者からの申請書等に係るものを加えたこと。
Ⅲ.社会保険労務士となる資格の要件の整備
社会保険労務士となる資格の要件として、試験合格又は全科目試験免除に加え2年間の実務経験を加えたこと。
Ⅳ.団体登録制への移行
社会保険労務士の免許制を連合会への登録制に改めたこと。
Ⅴ.社会保険労務士の権利及び義務
- 1. 信用失墜行為の禁止の対象者を、開業社会保険労務士からすべての社会保険労務士に拡大したこと。
- 2. 申請書等に関する付記の制度を設けたこと。
Ⅵ.懲戒
社会保険労務士の非違行為の態様に応じ社会保険労務士に対する懲戒処分の制度を整備するとともに、懲戒手続を整備したこと。
Ⅶ.社会保険労務士会及び連合会の事務の範囲の拡大等
- 1. 社会保険労務士会を任意設立制から強制設立制に改め、その会則の記載事項に会員の研修及び開業社会保険労務士の報酬に関する規定を加えたほか、社会保険労務士会への入会及び退会並びに所属社会保険労務士会会則の遵守義務に関する規定を設けたこと。
- 2. 連合会を任意設立制から強制設立制に改め、その会則の記載事項を整備するとともに会員社会保険労務士及び社会保険労務士会の連合会会則の遵守義務を設けたこと。
- 3. 連合会に登録の拒否及び登録の取消しについて審査を行う機関として資格審査会を置くこととしたこと。
Ⅷ.その他
- 1. 社会保険労務士会及び連合会の名称及び類似名称の使用制限規定を設けたこと。
- 2. 開業社会保険労務士の使用人等の秘密遵守義務に関する規定を設けたこと。
-
第3次法改正 【 昭和61年5月23日公布 昭和61年10月1日施行 】
Ⅰ.事務代理の新設
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告等に関する事務代理の制度を設けたこと。
Ⅱ.勤務社会保険労務士に関する規定の整備
勤務社会保険労務士に関する登録内容及び責務に関する規定を整備したこと。
Ⅲ.研修
社会保険労務士の研修受講義務及び事業主の勤務社会保険労務士に対する研修受講の便宜供与の努力義務を定めたこと。
-
第4次法改正 【 平成5年6月14日公布 平成6年4月1日施行 】
Ⅰ.職務内容の明確化
社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が、労務管理にあることを明確にし、試験科目の名称に労務管理の字句を加えたこと。
Ⅱ.登録即入会制への移行
- 1. 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた時に、社会保険労務士会の会員となることとしたこと。
- 2. 社会保険労務士は、登録抹消事由に該当することとなった時に、当然、所属社会保険労務士会を退会することとしたこと。
- 3. 登録即入会制の導入に伴い、所要の規定の整備を行ったこと等。
-
第5次法改正 【 平成10年5月6日公布 平成10年10月1日施行 】
Ⅰ.社会保険労務士試験の試験事務の連合会への委託等
主務大臣は、連合会に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)(試験事務)を行わせることができるものとし、連合会に試験事務が委託された場合の試験事務の実施に関する規定を設けたこと。
Ⅱ.社会保険労務士制度の充実
- 1. 社会保険労務士の業務
社会保険労務士が行う事務代理に、審査請求等を含めたこと。 - 2. 社会保険労務士会による注意勧告
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士がこの法律、この法律に基づく命令等に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずるべきことを勧告することができるものとしたこと。
- 1. 社会保険労務士の業務
-
第6次法改正 【 平成14年11月27日公布 平成15年4月1日施行 】
※報酬規定に関する必要記載事項を削除する部分については、公布日施行
Ⅰ.社会保険労務士の業務の見直し
- 1. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に定めた紛争調整委員会におけるあっせん代理を行うことを社会保険労務士の業務に追加したこと。
- 2. 労働社会保険諸法令に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を追加したこと。
Ⅱ.社会保険労務士試験の受験資格の緩和
受験資格に必要な従事期間を一律3年以上に改正したこと。
Ⅲ.登録事項の整備等
- 1. 社会保険労務士法人の社員又は使用人の登録事項を追加したこと。
- 2. 登録の取消事由を追加したこと。
(1)心身の故障により業務を行うことができない者に該当するに至ったとき
(2)2年以上継続して所在が不明であるとき
Ⅳ.社会保険労務士の権利及び義務に関する規定の整備
- 1. 業務を行い得ない事件に関する規定を追加したこと。
- 2. 非社会保険労務士との提携を禁止する規定を追加したこと。
Ⅴ.監督
- 1. 懲戒事由の通知等に関する規定を追加したこと。
- 2. 登録抹消の制限に関する規定を追加したこと。
- 3. 懲戒処分の通知に関する規定を追加したこと。
Ⅵ.社会保険労務士法人制度の創設
Ⅶ.社会保険労務士会及び連合会の会則の記載事項の整備
- 1. 支部を設けることができる規定を追加したこと。
- 2. 会則の記載事項から報酬に関する規定を削除したこと。
Ⅷ.社会保険労務士法人制度設立に伴う罰則の整備
-
第7次法改正 【平成17年6月17日公布 平成18年3月1日及び平成19年4月1日施行】
- ※1 紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験、労働争議不介入規定の削除については、
平成18年3月1日施行 - ※2 紛争解決手続代理業務の拡大、社会保険労務士法人に関する規定の整備については、
平成19年4月1日施行
Ⅰ.紛争解決手続代理業務の拡大
- 1. 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
- 2. 男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 3. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争目的価額が60万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
※上記代理業務には、当該手続に関する相談、和解の交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
Ⅱ.紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験
上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施し、合格してその旨の付記を受けた社会保険労務士のみ当該代理業務を行うことができるものとしたこと。
Ⅲ.労働争議不介入規定(法第23条)の削除
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除したこと。
Ⅳ.社会保険労務士法人に関する規定の整備
社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、上記代理業務を行うことができるものとし、当該代理業務は社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができるものとしたこと。
- ※1 紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験、労働争議不介入規定の削除については、
-
第8次法改正 【 平成26年11月21日公布 平成27年4月1日及び平成28年1月1日施行 】
- ※1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ、
補佐人制度の創設については、平成27年4月1日施行 - ※2 社員が1人の社会保険労務士法人については、平成28年1月1日施行
Ⅰ.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円に引き上げること。
Ⅱ.補佐人制度の創設
- 1. 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
- 2. 社会保険労務士法人が、上記1.の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
Ⅲ.社員が1人の社会保険労務士法人
社員が1人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
- ※1 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限額の引上げ、
-
第9次法改正【令和7年6月25日公布 下記Ⅰ・Ⅱは令和7年6月25日から、Ⅳは公布の日から起算して10日を経過した日から、Ⅲは令和7年10月1日から施行】
Ⅰ. 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」旨の規定を設けること。
Ⅱ.労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記すること。
Ⅲ.社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改めること。
Ⅳ.名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
- 1.社会保険労務士に類似する名称に「社労士」が含まれることを明記すること。
- 2.社会保険労務士法人に類似する名称に「社労士法人」が含まれることを明記すること。
- 3.社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士会」及び「全国社労士会連合会」が含まれることを明記すること。


 TOP
TOP